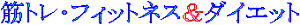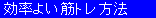効率のよい筋トレの順序と動作スピード
効率よく筋肉をつけるには、種目や鍛えたい部位の順序、動作スピード、回復時間を考慮した強度や量、頻度の調整が大切です。

効率よく鍛えられる筋トレの順序
大きな筋肉を先に鍛える
胸、背中、太ももなどの大きな筋肉を動かすには、これらとつながっている腕や肩などの、小さな筋肉も同時に動かさなければなりません。
小さな筋肉が疲れていると、大きな筋肉が疲れていなくても鍛えることができなくなってしまいます。
よって大きな筋肉を先に鍛えることが重要となります。
多関節種目を先に行う
スクワットやベンチプレスなどの多関節を使う種目は、カーフレイズやダンベルフライなどの単関節の種目より疲労が大きくなります。
(スクワットは膝関節と股関節を使う多関節種目、カーフレイズは膝関節のみの単関節種目です。)
よって、脚のトレーニングなら、スクワットの後にカーフレイズを行うようにします。
大胸筋のトレーニング
大胸筋のトレーニングでは、肩や腕の筋肉も同時に使います。
ベンチプレスでは、大胸筋のほかに肩の筋肉や上腕三頭筋が使われます。
ベンチプレスを行う前に、バーベルカールなどで腕のトレーニングをすると腕が疲れ、大胸筋は疲れていないのにバーベルが上げられなくなってしまいます。
鍛えたい部位からトレーニングする
トレーニングの始めは、疲労が少なく集中できる状態にあるので、一番鍛えたい部位を先にトレーニングすることで、効率が上がります。
また、パワーや瞬発力を必要とする種目も疲労が少ない状態で行うことが望ましいです。
姿勢維持筋の種目は後で行う
体幹の筋肉を先に鍛えると、他の種目を行う際に姿勢を維持することが難しくなります。
よって、腹筋やバックエクステンションなどはトレーニングの後半で行うようにします。
同じ筋肉を連続して使わない
当然ですが、同じ筋肉ばかりを連続して鍛えると疲労が早まります。
上半身を鍛えたら下半身、筋肉を曲げる種目と伸ばす種目、押す動作と引く動作のように、順番に行うようにします。
ウォーミングアップはほどほどに
ウォーミングアップは体を温める程度にします。
筋トレの前に脂肪が燃焼するような有酸素運動などを行なうと、成長ホルモンの分泌が抑制されてしまい、せっかく筋トレをしても筋肉がつきにくくなってしまいます。
筋肥大に効果的な動作スピード
コンセントリックとエキセントリック
筋肉の動作は、コンセントリック(挙げる)、エキセントリック(下ろす)の繰り返しですが、下ろすの方が大きな力を発揮できます。
例えば、持ち上げられないバーベルを下ろすだけならできることがあります。
筋トレでは、エキセントリックのトレーニング効果はとても大きいです。
1秒で上げて3秒で下ろす
ダンベルやバーベルを下ろすエキセントリック動作が筋力アップには大切です。
エキセントリック動作では、低負荷でも速筋線維が動員されやすい特徴があります。
5秒、10秒かけて下ろせば筋肉に大きな負荷をかけられますが、疲れて回数をこなせなくなってしまいます。
数回しか反復できなくなったら本末転倒です。
効率よく筋肉をつけるには、1秒で上げて3秒かけて下ろし、10回くらいできる負荷で行うことが重要です。
筋肥大トレーニングの動作スピード
筋肥大トレーニングの動作スピードは、1秒で上げて3秒で下ろすようにします。
スピードが速くなると、フォームが崩れたり、勢いがついたりします。
勢いがつくと、動作の始めだけ筋肉が使われ、後は惰性で十分な効果が得られません。
また、さまざまな筋肉が使われて、鍛えたい筋肉に掛かる負荷が小さくなってしまいます。
スロートレーニング
動作を遅くするスロートレーニングでは、成長ホルモンの分泌が促進されて、筋肥大に効果があります。
例えば、腕立て伏せなど比較的軽い負荷でも、体を持ち上げる・下ろす動作をそれぞれ5秒程度かけることにより、血流が制限された加圧トレーニングのような状態になり、乳酸の蓄積などにより筋肥大が促されます。
低負荷なので安全にトレーニングできますが、スピードが遅いのでパワーが低下することがあります。


|
ダンベル 片手35kg
アイロテック
ハードトレーニーのためのスペシャルセット。通常のダンベルでは装着できない重量調整が可能です。
ダンベルシャフト55cm(3kg)×1本、5kgプレート×6枚、1.25kgプレート×2
|


|
マルチシットアップベンチ【耐過重300kg】
YouTen
腹筋・背筋のトレーニングに使う「シットアップベンチ」とダンベルトレーニングに使う「フラットベンチ」の両方の機能を備えた、1台2役の便利なトレーニングベンチです。折り畳めます。
サイズ:W49×D117.5×H71.5〜78.5cm、重量12kg
|
|